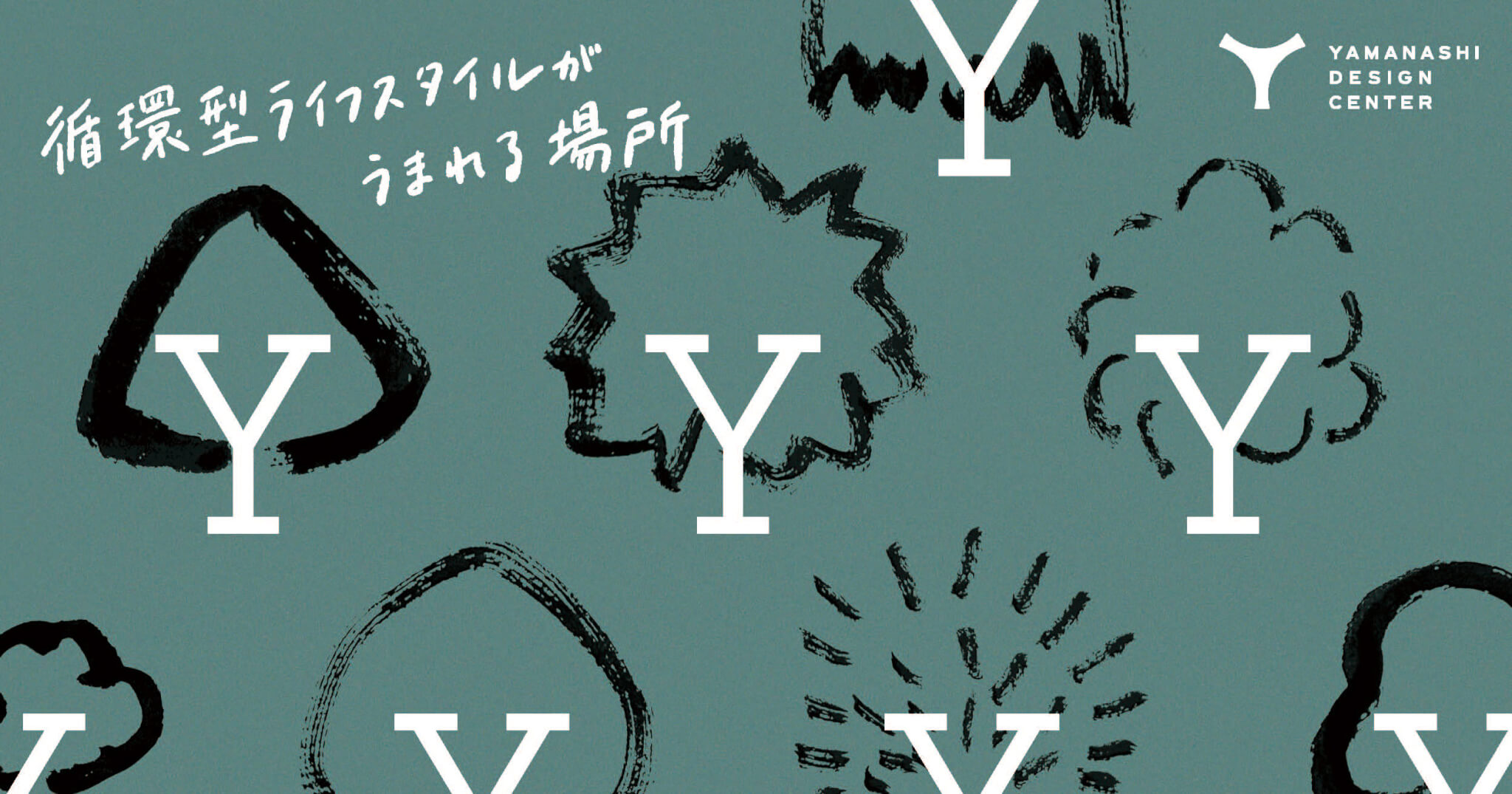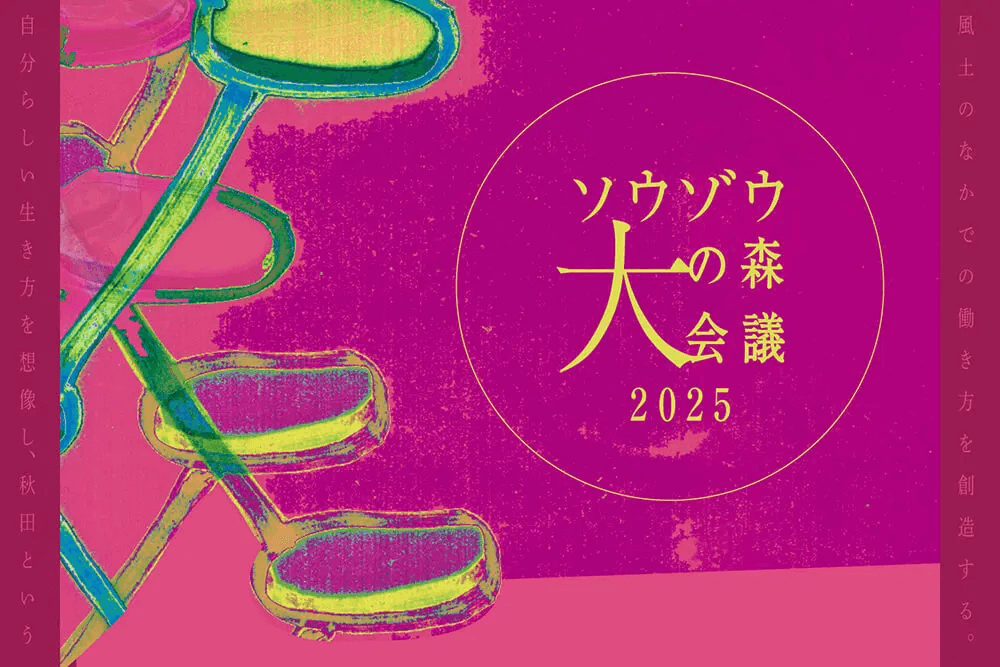「建物ストック」という言葉をご存知でしょうか。過去に建築され、今なお存在する建築物の総称です。なかでも住宅のストック数は世帯数をゆうに超え、2023年には全国の空き家が過去最多の900万戸を記録しました。
建物ストックは歴史と文化が染み込んだ大切な資産である反面、現代のライフスタイルに合わないものや安全性の低いものも少なくありません。資産価値を生み、あるいは維持しながら建物ストックを次世代に継承するには、どのような工夫ができるでしょうか。
本イベントでは、HAGISOの宮崎晃吉さん、巻組の渡邊享子さんをゲストに迎え、建物ストックの次世代への継承について事例を交え議論しました。
執筆:吉澤 瑠美
思い出の詰まった木賃アパートを開かれた場に

東京の下町・谷中にある「HAGISO」のルーツは、戦後復興のさなかに建てられた築70年の木賃アパート「萩荘」です。宮崎さんは偶然出会った大家さんと意気投合し、空き家となっていた萩荘で大学の仲間とともに暮らし始めました。
やがて宮崎さんたちは大学を卒業し萩荘を巣立ちましたが、その後萩荘取り壊しの計画を聞き、有志で開催したアートイベント「ハギエンナーレ 2012」は1500名近くの人々が来場する盛況に。大家さんと協議の末、最小文化複合施設「HAGISO」としてリスタートすることになりました。今ではカフェとギャラリー・イベントスペースを中心に、さまざまな人が集う場になっています。

建物ストックの再利用で現代に蘇る「まちに住む感覚」
宮崎さんはHAGISOの一室の事務所で暮らし始めましたが、築70年のHAGISOに風呂はなし、台所も炊事向きではありません。おのずと、近所の銭湯や飲食店を利用する生活が始まりました。「台所や風呂を街に借りる生活は不便に見えますが、見方を変えれば街全体が自分の家のようなもの」と宮崎さん。この「まちに住む」体験を広く提供すべく誕生したのが宿泊施設「hanare」です。
空き家を改装したhanareにはお風呂もキッチンもありません。小さな宿からチケットとタオルを持って銭湯へ行き、風呂上がりにバーで軽く一杯。HAGISOのカフェで朝食をとり、自転車店のレンタサイクルで散策に出かける。近隣の協力店も徐々に増え、個店の集合体である下町ならではの宿泊体験は、唯一無二の価値を旅行客に提供しています。

街の中でその場所がどのような役割を担うのか?
HAGISOの営むジェラート店「asatte」は、谷中に多く見られる細い路地が特徴です。路地の先に広がる裏庭は憩いの場であるとともに、ときには子どもマルシェなどのイベント会場にもなります。子どもマルシェには大人は立入禁止。つかの間親元を離れ、子どもだけの小さな社会で売り買いを体験するマルシェは、近隣地域の親子に人気の企画となっています。

また、宮崎さんは、谷中だけでなく他地域の建物活用プロジェクトも手掛けています。郷里・群馬県の旧前橋信用金庫本店をリノベーションするプロジェクトでは、駐車場を公園に、そして2階には読書ができるフリースペースを増床。15時で銀行の営業が終了した後も、カフェでくつろぐ人や学校帰りの中高生が訪れるようになり、活気が生まれました。
長く前橋市民の生活の中心にあったこの場所は、今でも地域のランドマークの中心に位置していることから「ここで休憩して次の場所へ行ける、中継点のような場所」になることをイメージしてリノベーションに取り組んだと宮崎さん。谷中での活動から一貫する「この場所が街でどういう役割を担うのか」という問いは、建物に新しい価値をもたらしています。
街を面白くする移住者たちが住める場所をつくる
巻組の始まりは2011年、東日本大震災により就職活動がすべてストップした渡邊さんが、「何かできることはないか」と東京から石巻へ向かったことでした。当時の石巻では復興が長期化するなか、ボランティアで訪れた人々が石巻で事業を立ち上げようとしましたが、移住者が借りられる家は非常に少なく、ほとんどが実現しなかったといいます。一方、震災の影響で市の人口は約2万人減少。新築の災害復興住宅も建ちましたが、市内では戸建住宅を中心に1万戸以上が余るという不均衡が問題となっていました。

「他地域では移住者が地方を面白くしているのに、移住者が定着しないのはもったいない」と渡邊さんは考え、空き家を改修してシェアハウス等の賃貸物件にする活動を始めました。
独自のライフスタイルを作れる人が街の価値を上げる
こうして立ち上げたさまざまなシェア空間に集まったのは、家具を作るクリエイター、衣類を直すお針子さん、狩猟免許を持つアーティストなど、個性的な方ばかり。一般的な賃貸住宅では条件に合わず、望んだ生活が実現できずにいた人々を、ハグロBASEは柔軟に受け入れました。

現代の生活にそぐわない古い造りを改修した家は、住人たちから「むしろ好都合・便利」と好評を得ました。小上がりを展示ギャラリーにする人あり、土間を作業場にする人あり。一般的な賃貸住宅の規格に当てはまらない人々が自由な暮らしを獲得するために試行錯誤する姿は、とても生き生きして見えたといいます。
現在では定住者だけでなく、さまざまな形態の居住者をサポートしている巻組。ある東京の会社員は巻組のシェアハウスを第二の住処とし、毎月石巻と東京を行き来しながら新しいゲストハウス開業に積極的に参加しています。また、日本滞在中の宿代わりに空き家を購入したいという訪日観光客には、物件探しからリノベーションまで支援するサービスを提供しています。

渡邊さんは「独自のライフスタイルを作れる人の存在が、街の価値を高める」と語ります。関係人口を巻き込むなど多様なライフスタイルを視野に入れた建物ストックの活用は、地方創生のヒントになるかもしれません。
豊富な建物ストックを、アイデアの力で次世代の宝に変換する
両名のキーノートセッションを振り返り、モデレーターの仁井谷は建物ストックへの向き合い方の違いに関心を示します。
宮崎さんに幅広い事業のモチベーションを尋ねると、「気づいたらこうなっていた」と笑いつつ、多様なバックグラウンドを持つ人々との出会いが事業の広がりを生んでいると答えます。また、「大家さんとの関係性は大切にしている」と語り、建物所有者の理解や連帯も事業を成り立たせる大きな要因であると補足しました。

一方、利用者による個性的な建物活用が印象的な巻組の取り組みですが、渡邊さんは「別段意図したものではなかった」と当時を回想します。市場の小ささ、限られた予算などの制約がある中、利用者のハードルを下げたことで「偶然面白い人たちが最初に入居してくれて道が拓けた」と語りました。
共創のヒントは「バタフライエフェクト」「迂回する経済」
最後に、会場を代表してQ0の林から「デベロッパーのような大企業からパートナーとしてオファーがあった場合、どのような共創が考えられるか」という問いが投げかけられました。
大企業のプロジェクトとなれば、予算も規模も大きな事業が期待できる一方、短期的な視点で利益を追求することが懸念されます。渡邊さんは、「大きな収益は見込めなくても節税にはなる、ぐらいの折衷案を見出せるとありがたい」とバタフライエフェクトに期待を寄せました。宮崎さんも、吉江俊『〈迂回する経済〉の都市論』(学芸出版社)を紹介し、「目先の利益に終始せず、長期的に建物や街の価値を考えられる人たちと共創したい」と語りました。

両名の話を頷きながら聞いていた林は、「新築ではない、リノベーションが脚光を浴びて20年が経過した今、その先の一手が求められている。二人の活動は手がかりになるのでは」とコメント。「今後もそれぞれの立場で考えていけたら」と会場の参加者にも引き続きの議論を呼びかけました。